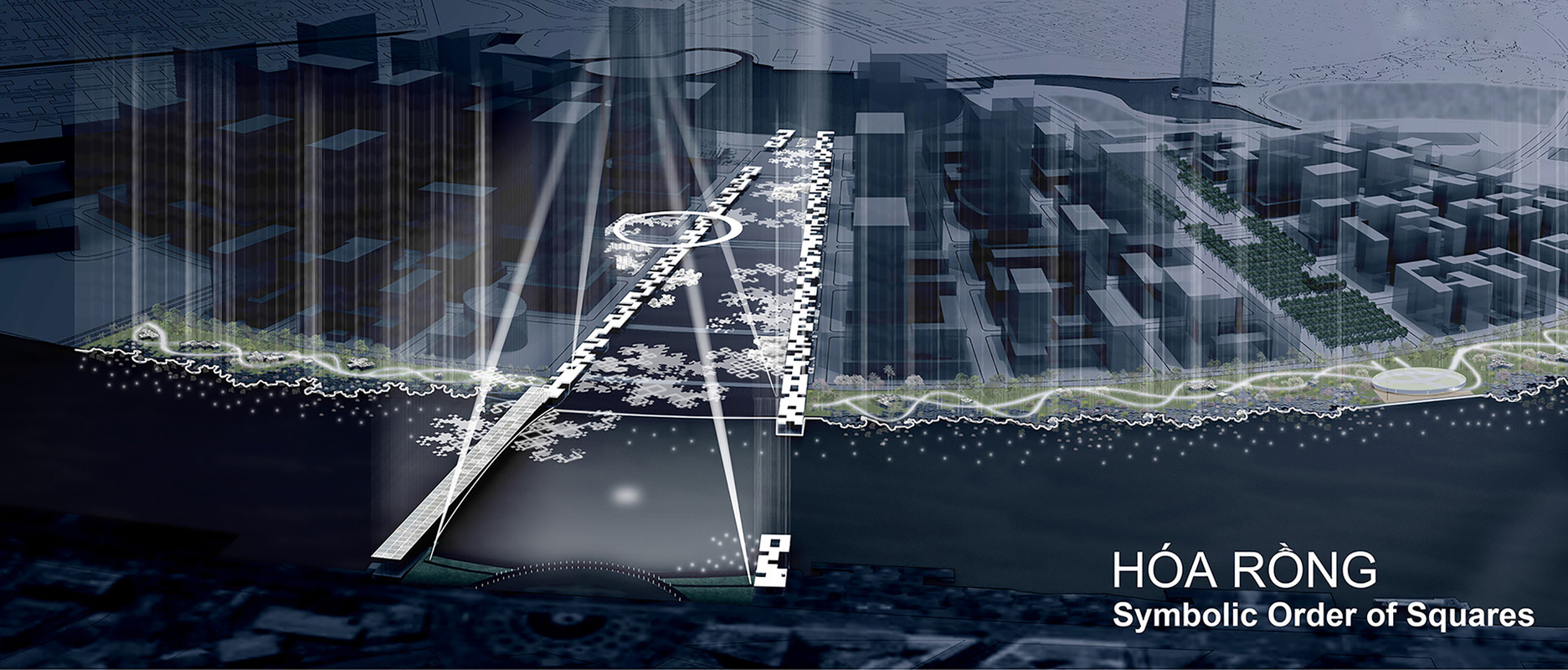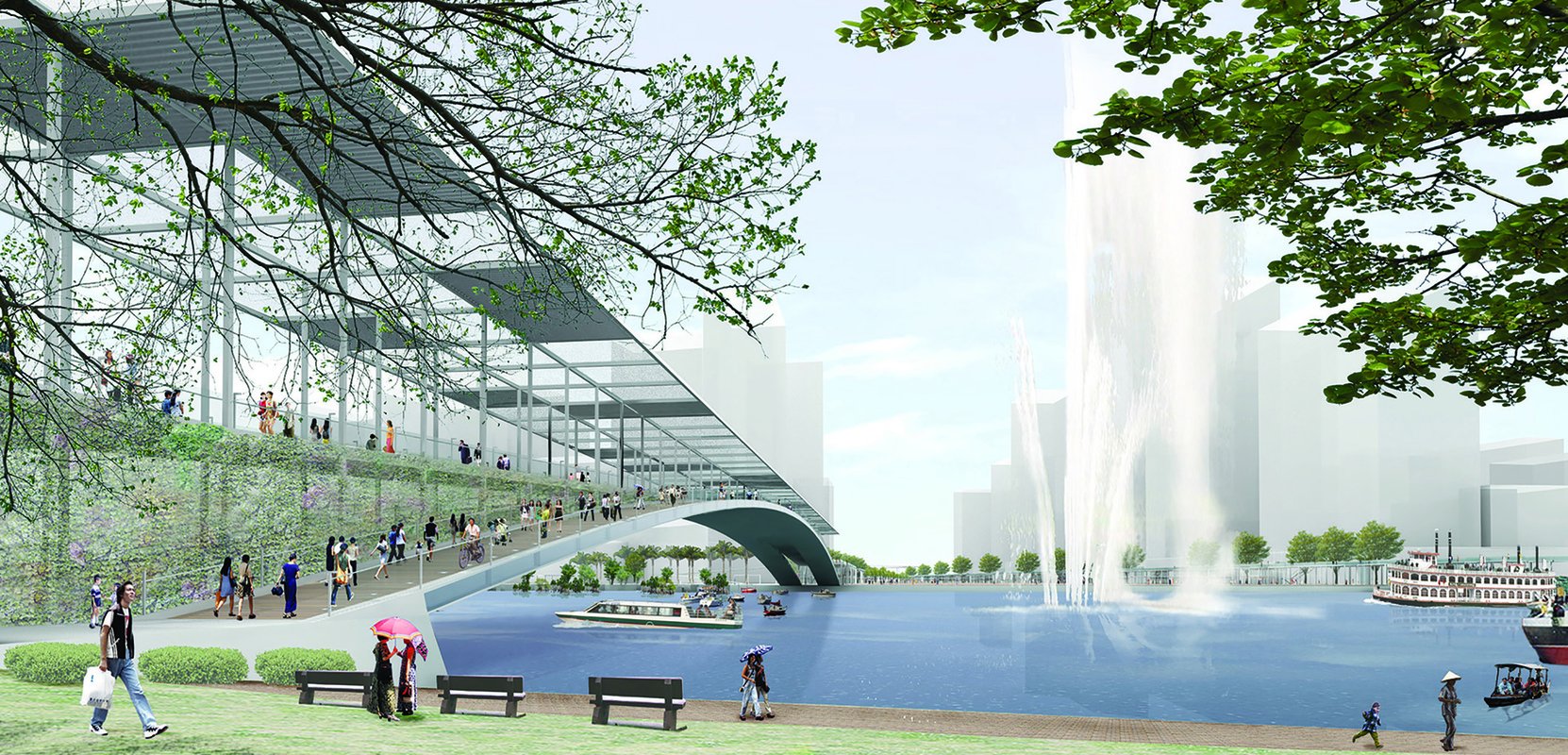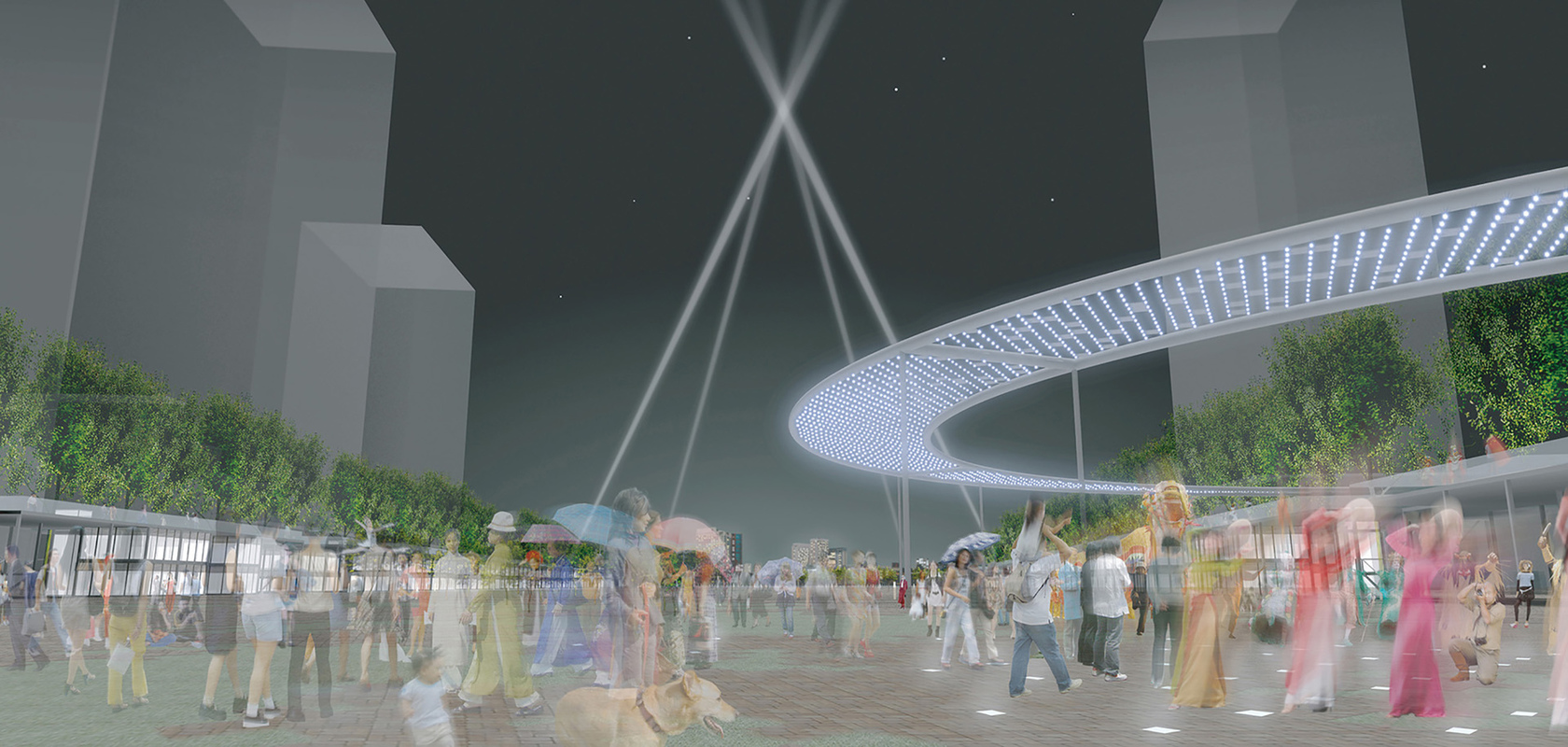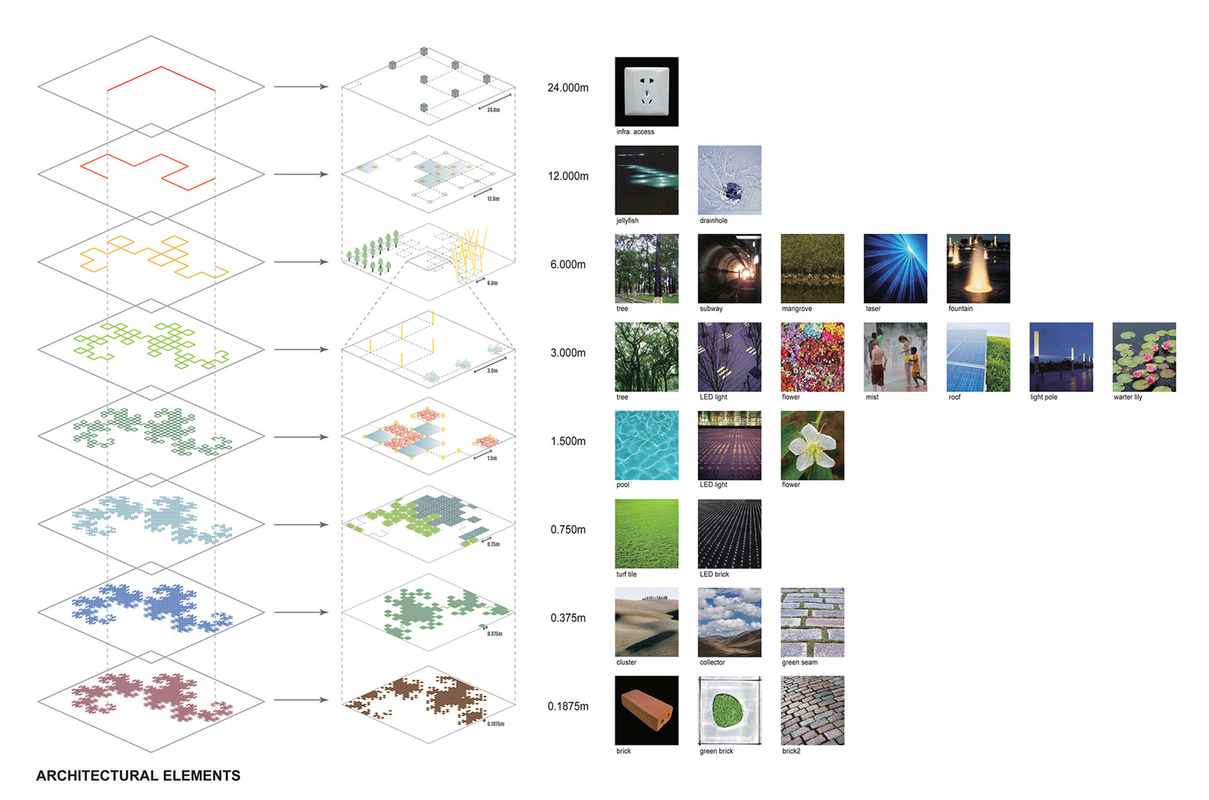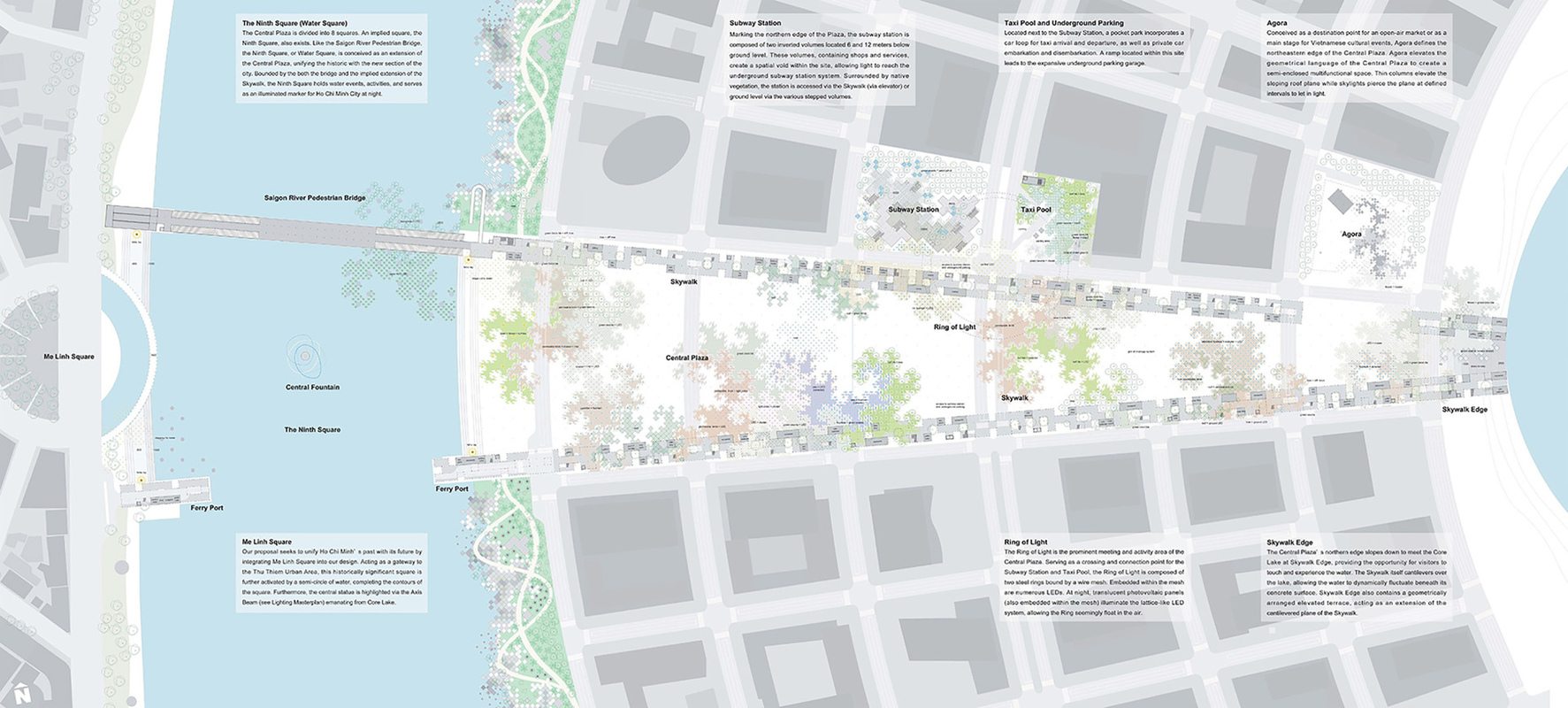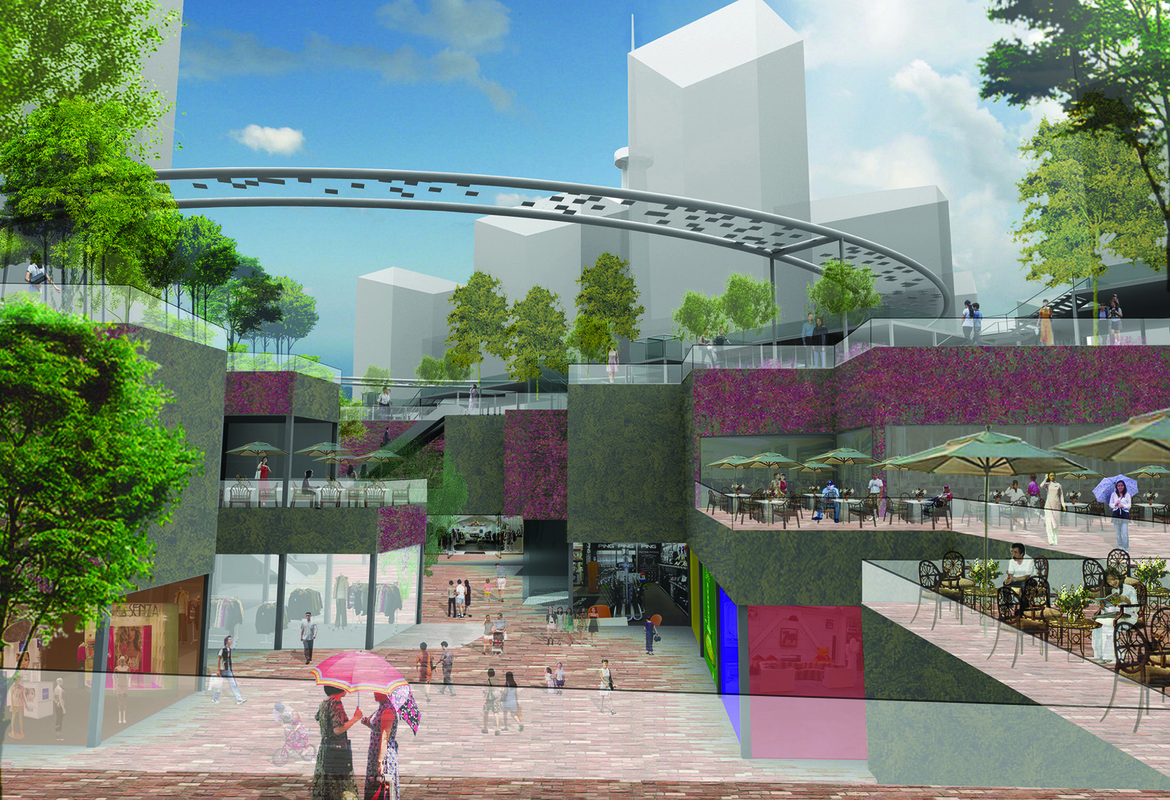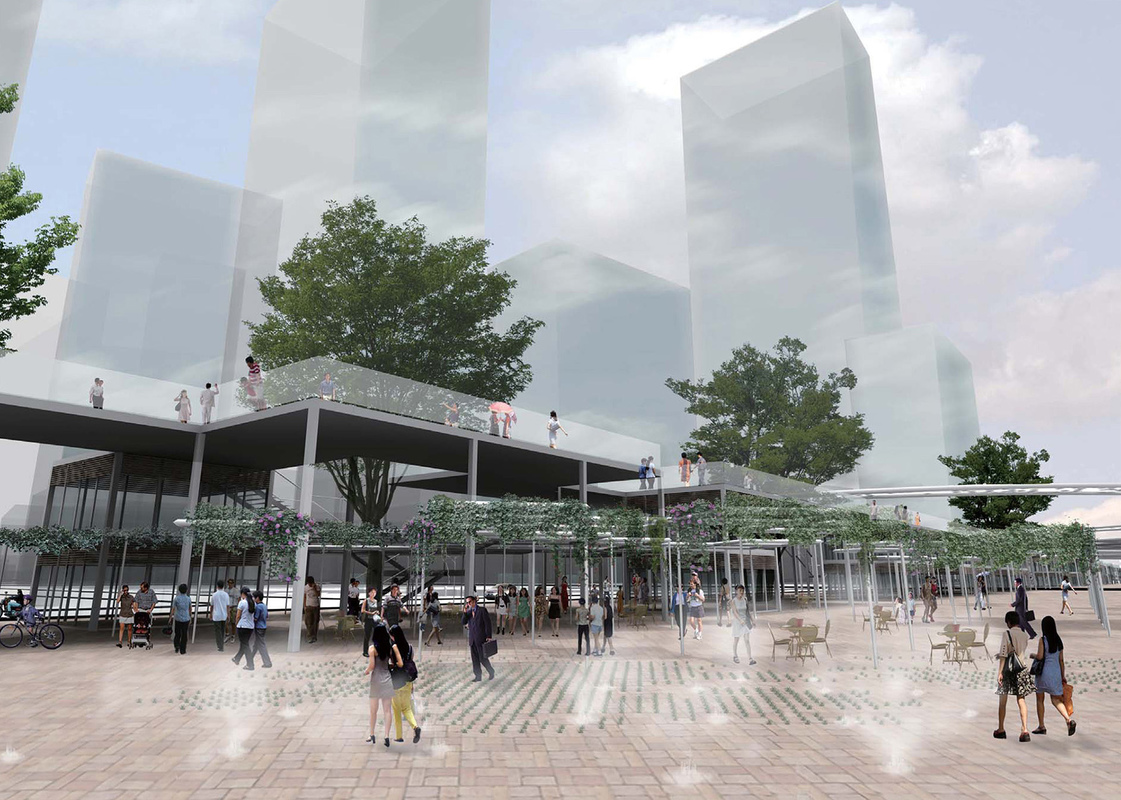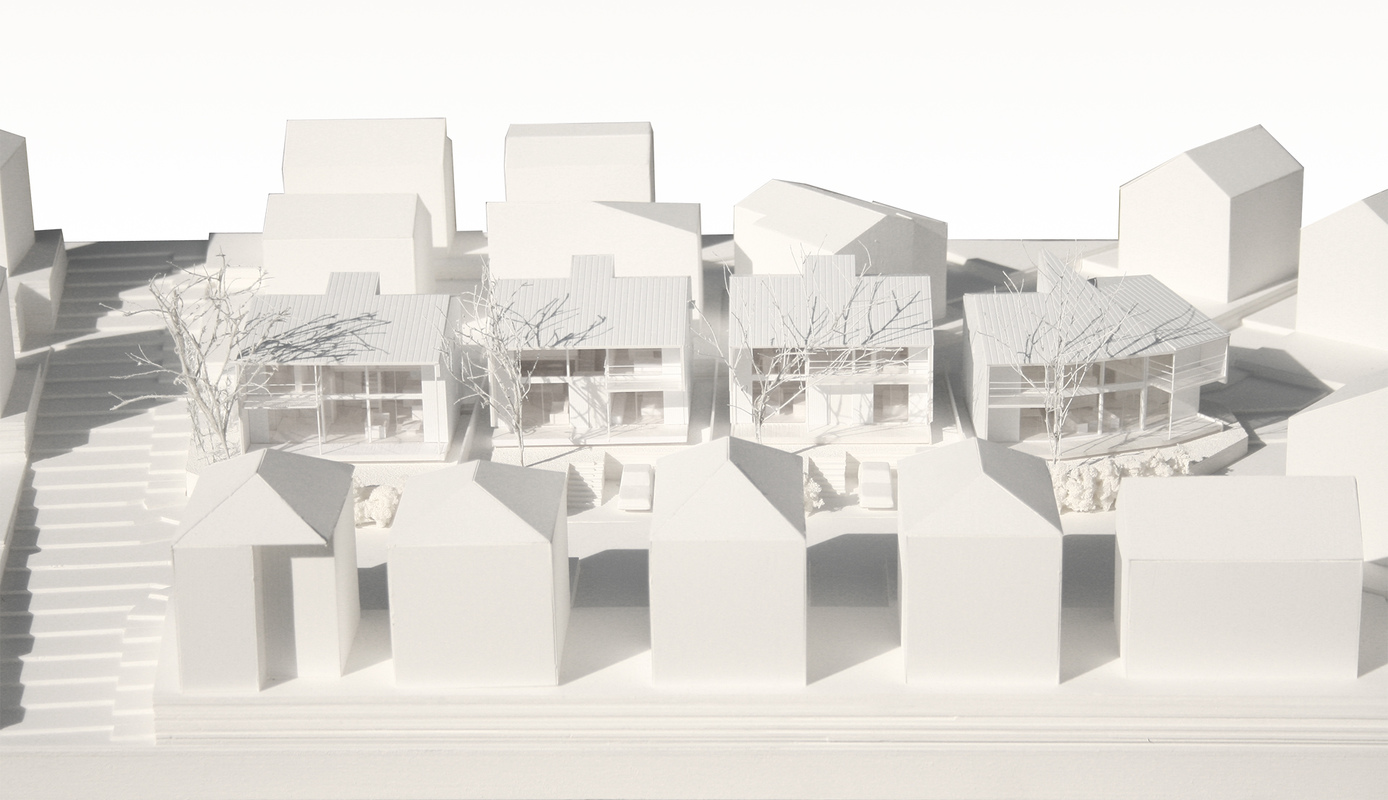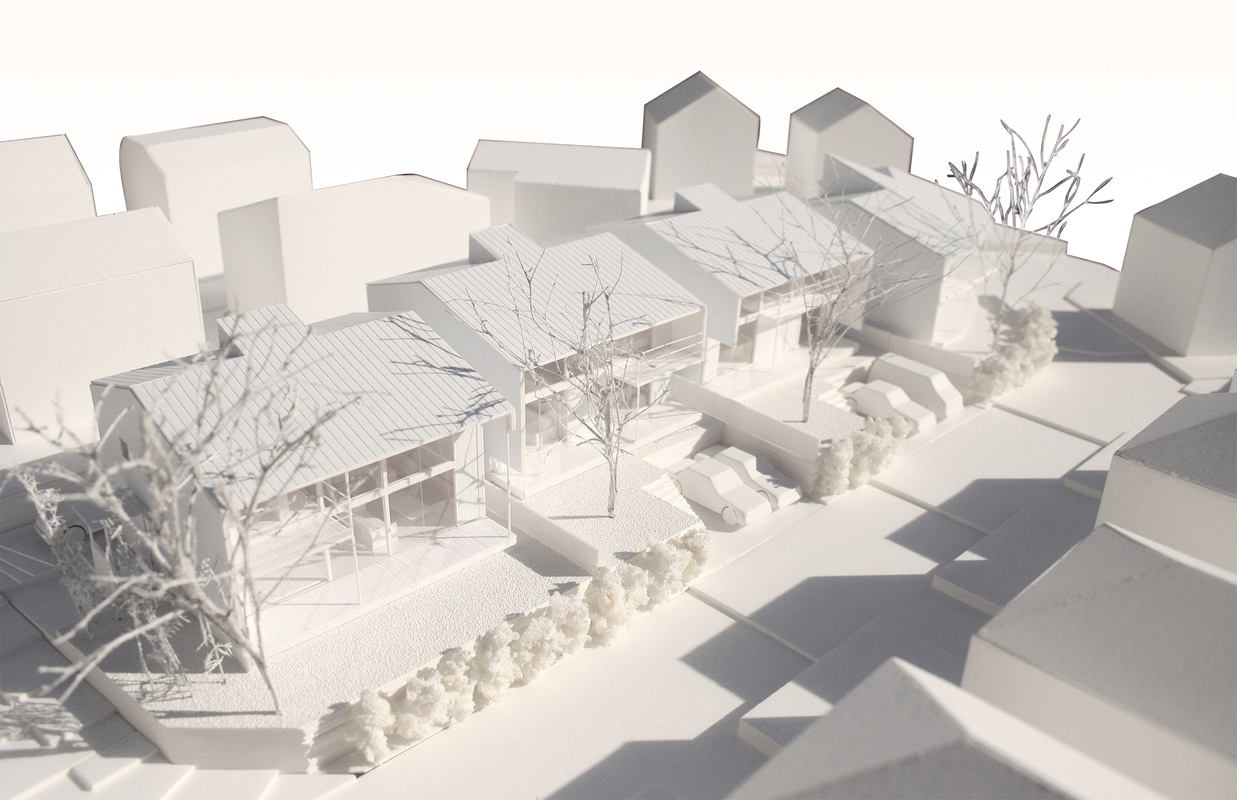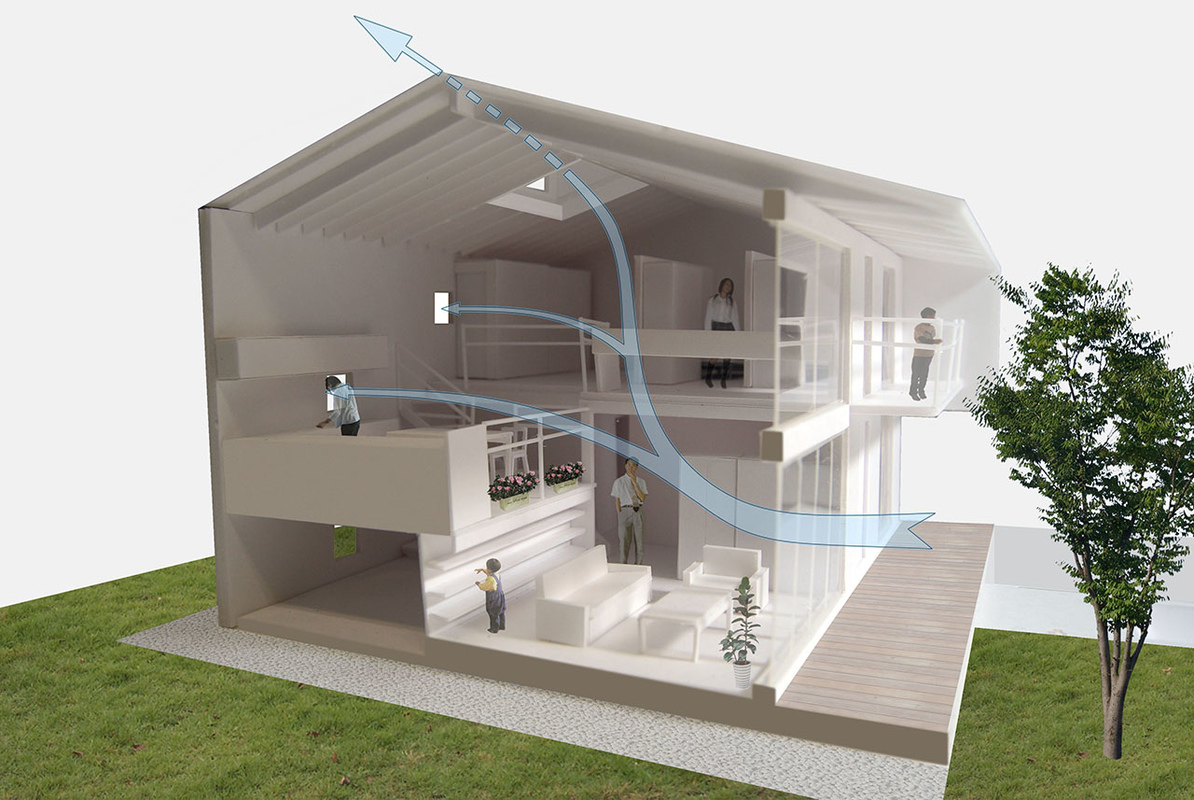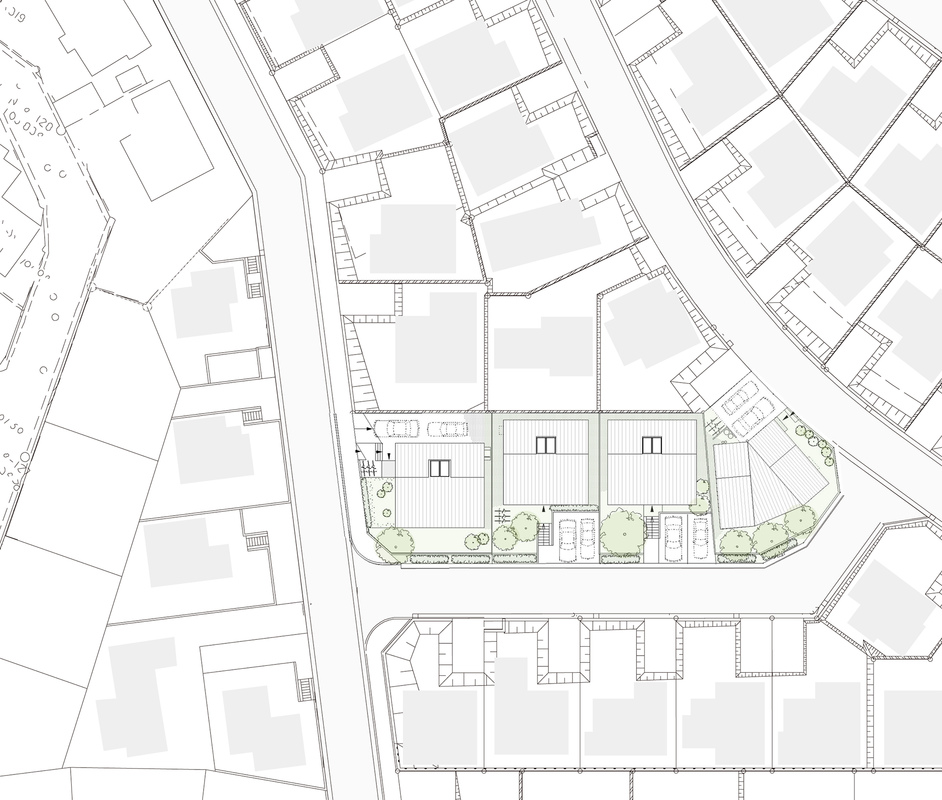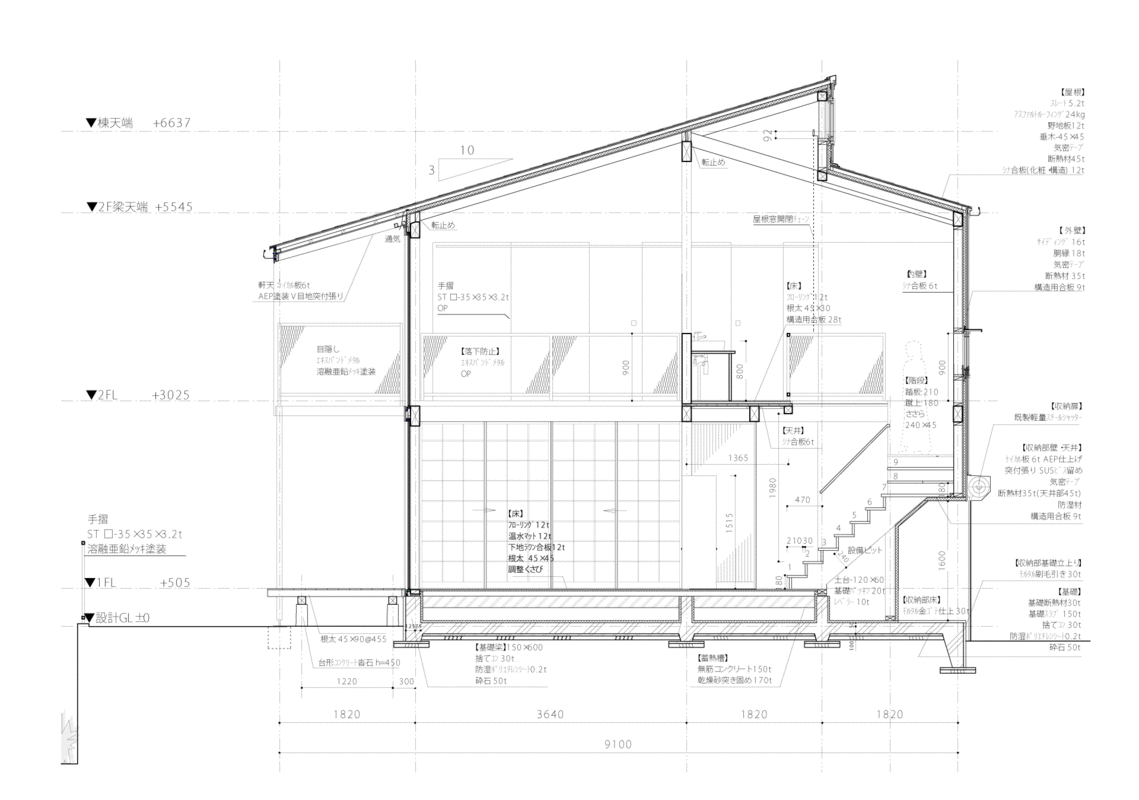建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏
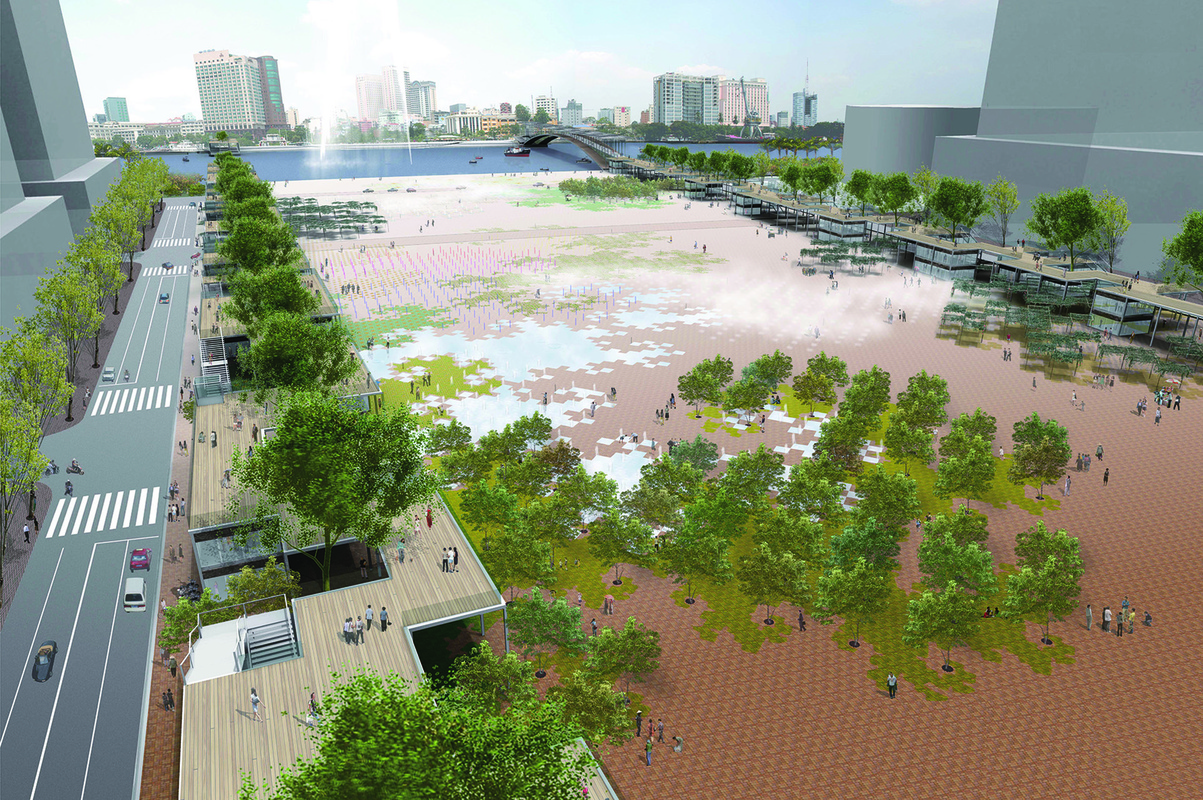
建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

建築家:鴻野吉宏

 この建築家に相談したい
この建築家に相談したい